Uncovering the two crises Japan has faced due to over-cutting of forests
Updated by 長澤 光太郎 on May 19, 2025, 3:07 PM JST
Kotaro NAGASAWA
(一社)プラチナ構想ネットワーク
1958年東京生まれ。(株)三菱総合研究所でインフラストラクチャー、社会保障等の調査研究に従事。入社から数年間、治山治水のプロジェクトに携わり、当時の多くの河川系有識者から国土を100年、1000年単位で考える姿勢を仕込まれる。現在は三菱総合研究所顧問。学校法人十文字学園監事、東京都市大学非常勤講師を兼ねる。共著書等に「インフラストラクチャー概論」「共領域からの新・戦略」「還暦後の40年」。博士(工学)。
千葉徳爾『はげ山の研究』を読むと、江戸時代には激しい森林荒廃があったことがわかる。では、日本史全体を俯瞰するとどうなるのだろう。そんな問いにコンパクトかつ的確に回答してくれる書物の一つがコンラッド・タットマン著『日本人はどのように森をつくってきたのか』(熊崎実訳、築地書館、1998年)である。壮大な題名だがわずか200頁、翻訳も素晴らしく非常に読みやすい一冊である。
内容の要点は、日本では古代から近世にかけて、木材需要の高まりによる森林の過剰伐採で2度の危機に直面したが、政治的・自主的な規制と創意工夫により、持続可能な林業を確立したというもの。書名のとおり、日本の森林は各時代における日本人の叡智によって「つくられて」きたのだ、というのが米国人学者タットマン教授のメッセージ。彼は、欧米や中国では少数の例外を除いて、人間活動で失われた森林は回復できていないと指摘する。
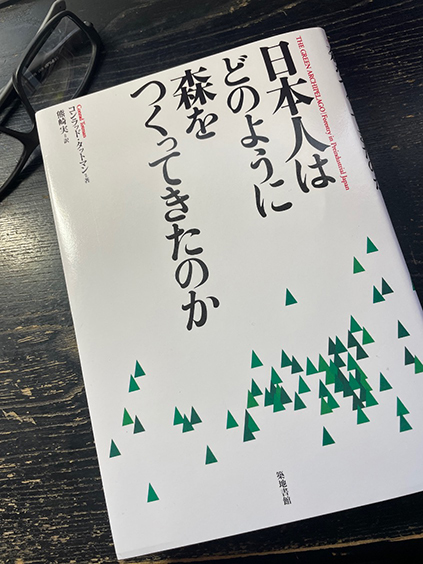
以下は私なりに整理した本書の要約である。
古代の日本人は森林と共存していたが、大陸からの文明を取り込むたびに森林からの収奪が激しくなった。まず稲作の普及が水田拡大のための林地伐採を促した。青銅や鉄の生産は木炭を大量に使用した。鉄器の進歩は手斧や鋸など伐木の道具を進化させた。そして6世紀の中頃、大陸からの移民たちが石の土台、ホゾとホゾ穴の木組、屋根瓦など大規模建築物を実現する構造技術を持ち込み、空前の建築ブームが起きて森林からの収奪が加速した。それは大和朝廷が日本全体の統治者として地盤を確立した時期に重なる。
私たちは、古代には遷都がよく行われていたことを知っている。遷都先の土地はどういう理由で選ばれるのか。「建築用の木材が入手容易」であることは間違いなく重要な要素だった。
600年頃からの飛鳥(奈良県南部)、難波(大阪府西部)、大津(滋賀県東部)などの都の造営で、現在の近畿地方中心部に近い森林の木は著しく減少しており、710年の平城京の建設には滋賀県北部、三重県などから採り出された木材が使われた。784年には桓武天皇が京都府南部の長岡に遷都し、わずか10年後には平安京が造営された。このとき用いられた木材を供給したのは、当時の周辺地域で唯一まとまって残る原生林があった山城国(京都府南部)から丹波地域(同北部)にかけての地域であった。
都の造営では、天皇一族をはじめとする貴族の住居や記念碑的な建築に加えて宗教的な大建築が多く行われる。その代表例は奈良の東大寺で、記録によれば10万石の部材(木材)が使用された。これは現代の戸建住宅3,000戸分に相当し、しかも良木を選別して使用していることを考え合わせれば、伐採された森林は900haに及ぶだろう、とタットマンは記す。そして東大寺の建築規模は当時建設された寺院建築総量の1%程度と推計し、おそらく寺院建築だけで9万ha(東京ドーム2万個分)の檜の原生林が皆伐されており、もし択伐形式であったならばその面積はさらに大きくなるはずだという。
この激越な古代の収奪は当然長続きせず、平安京が造営される頃には畿内周辺には建設用木材がほとんどなくなっていただろう、というのが本書の見方である。
2回目の森林破壊は戦国時代末期から始まった。豊臣秀吉が乱世を平定して記念建築物の建設に邁進し始めるのが16世紀末である。大阪城の造営、朝鮮出兵のための九州での城郭造り、伏見の巨大な稜堡、京都の聚楽第、そして東大寺よりもさらに巨大な大仏を納める方広寺。これらに使用する最高級の木材は和歌山県、岐阜県、静岡県、高知県、宮崎県さらには秋田県の各地域で伐採され建設地に運び込まれた。森林からの収奪は全国に及んだ。
秀吉の後に天下を平定した徳川家康も江戸城、駿府城、名古屋城、彦根城、膳所城、篠山城、亀山城、二条城などのほか、桂離宮をはじめとする文化的な建築に惜しみなく全国の良材を投入した(ちなみに本書によれば江戸城の木材使用量は東大寺の5倍である)。そして何より、新首都である江戸の整備に膨大な量の木材が用いられた。中央集権の確立により、必要な木材は全国から集められた。
加えて、都市の大火が巨大な木材需要を作り出した。江戸の例では10ブロック以上を焼き尽くす大火が2年9か月に1回の頻度で起きていた。1657年と1772年には江戸の街を半分以上焼失させる大火が起きている。この時代には日本には原生林はほとんどなくなっていたので、江戸再建のために日本中の広大な森林から木材が伐り出されたはずだと本書は記す。
江戸時代は人口増加もあり、権力者による収奪に加えて地域生活の必要資源としても森林は巨大な需要に応えなければならなかった。このため17世紀末には北海道を除く日本列島から価値の高い天然林はほぼ消滅していたとされる。熊沢蕃山(1619-1691)は「この国の十の山のうち八までが裸になった」と記している。江戸のほとんどを焼き尽くした1657年の大火の後、幕府は首都再建のため木材の拠出を広く求めた。秀吉の時代に豊富な木材資源を提供した土佐の山内氏の返答は「領内の山は伐り尽くされた。スギもヒノキもなくなっているから、将軍が望んでおられるような良材を工面することはできない」であった。=後編に続く(プラチナ構想ネットワーク理事 長澤光太郎)