What happens if we leave forests unattended? From the perspective of "potential natural vegetation"
Updated by 長澤 光太郎 on December 19, 2025, 9:14 PM JST
Kotaro NAGASAWA
(一社)プラチナ構想ネットワーク
1958年東京生まれ。(株)三菱総合研究所でインフラストラクチャー、社会保障等の調査研究に従事。入社から数年間、治山治水のプロジェクトに携わり、当時の多くの河川系有識者から国土を100年、1000年単位で考える姿勢を仕込まれる。現在は三菱総合研究所顧問。学校法人十文字学園監事、東京都市大学非常勤講師を兼ねる。共著書等に「インフラストラクチャー概論」「共領域からの新・戦略」「還暦後の40年」。博士(工学)。
前回の『杉のきた道』(遠山富太郎)の読後に、そういえばスギ(ヒノキ科スギ属)は日本独自だが、潜在自然植生とは言われていないな、と考えた。潜在自然植生とは、人間が介入を停止した後、その森が向かう極相林(林相の最終形態)の植生をいう。日本の場合、西南日本では照葉樹林(シイ・カシ類)、東北日本ではブナ林・ミズナラ林とされている。つまり人が介入しなければ、超長期ではスギは消えていくということだ。森林を放置したらどうなるかを考えることは、我々と自然との関係を考える上で、とても重要だと思う。
潜在自然植生の用語は、故宮脇昭氏がドイツから日本に持ち帰り、広く普及させた。そこで、改めて宮脇氏の著作を手に取ることにした。今回、『植物と人間〜生物社会のバランス〜』(NHKブックス・1970年)を選んだのは、著者が「私の全てがあの本に詰まっている」と言っていたからである。内容が濃く、読了までに多くの時間を費やした。
これは確かに名著だと思う。多方面にわたって、深く考えさせられる記述がある。要約は難しい。以下では、私が興味を引かれた部分をまとめた。発刊から五十年以上が経過しており、現代の目から見れば訂正すべき点があるかもしれないが、その点も含めてご容赦いただければ幸いである。
生き物が存在する空間を生物圏という。それは極めて狭い。水中で植物は光合成を営む限界があり水深300mまでである。動物類は深度10kmだ。空中では鳥がせいぜい地上400m、飛散する微生物や花粉が10km。つまり、大きく見て地表±10kmの、地球にとっては卵の殻のような、ごくごく限られた空間にしか生物は存在しない。
生物圏の主役は植物である。なぜなら生物の体積合計の9割は植物なのだから。動物は1割に過ぎず、しかもそのほとんどは魚類だ。ある推計では、地球上の人間を立方体の箱に隙間なく詰めたら一辺の長さは1kmで足りるという。(※注:本書刊行は1970年。当時の世界人口は37億人)
生物圏は共同体である。蛇とカエルのような捕食関係も含めて、全ての場で動的均衡状態が保たれている。人間も植物も、その構造の中にいる。
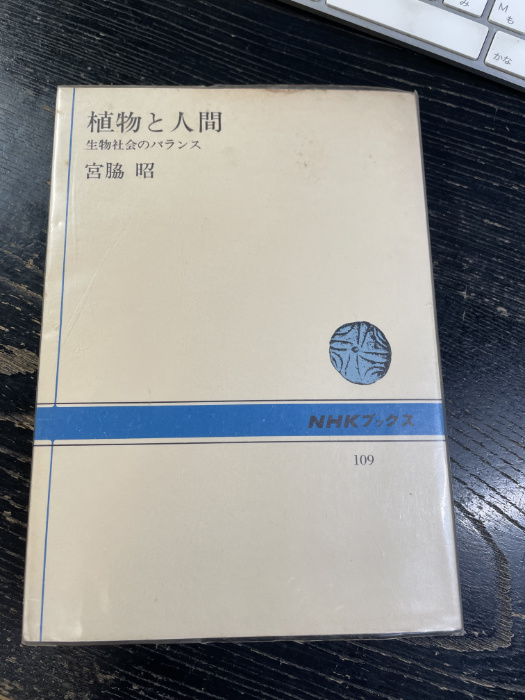
生物圏の主役たる植物は、しかし自由に生きる場所を選べない。まず気候や気象、土壌などに制約される。そして植物間の内的秩序がある。植物Aの生理的に最適な場所で、植物Bが相対的に強ければ場所を譲らざるを得ないのだ。結果的に植物Aは生理的最適ではなく生態的最適な場所で生きることになる。
本書から引用する。「移動能力のない植物は(中略)人間以上に、種本来の最適生育地からはずされて、我慢しながら何とか芽生え、生長し、花を咲かせている。」「植物群落とは、その中で個々の植物同士は競争し、我慢し、生活の場を住み分けて共存しながら、時間的にも空間的にも動的均衡状態を保っている生物社会の原型である。」「(共存は重要であり:引用者註)強すぎる植物は、その生物社会を混乱状態におとしいれるばかりでなく、環境を悪化して、自らの生存もついには危うくする。」
植物群落は、生物個体と同じように、発生し、繁茂し、老衰し、やがて他の群落に置き換わる。これを遷移という。遷移は、発達状況に応じて先駆相(初期段階)、最適相(最も繁茂)、退化相(終末相)に区分される。また、人間の影響を受けない遷移を一次遷移(自然遷移)、人間による改変を二次遷移(人為遷移)と呼ぶ。
「植物と人間」は、植物群落の遷移をことのほか重視する。「一年生雑草群落などは他の多年生の草本群落に代わる。同様に多年生草本植物群は低木林におきかえられる。ついで陽樹高木林、陰生高木林というように、その立地の地域気候条件とつりあった終局群落に達するまで、群落と環境の交互交代が続けられる。」
さらに具体的な例が挙げられる。「いわゆる耕作放棄畑では、その年は、畑地雑草のメヒシバなどが、かつてみられないほど繁茂する。しかしすぐに翌年には、より草丈の高くなる路傍や空地に生育していたヒメムカシヨモギ、ヒメジョオン、オオアレチノギクなどの路傍雑草が、畑地雑草にとってかわって優占する。四〜五年には、多年生草本植物のススキ、チガヤ、トダシバのイネ科草原となる。ついでキブシ、ヌルデ、クズなどのマント群落が被い、一〇〜一五年目にはコナラ-クヌギの雑木林に移行する。八〇年ないし一〇〇年たてば、その土地固有の自然林、関東以西の海岸ぞいにはシイ、タブ林、内陸ではカシ類の常緑広葉樹林に発達する。」

歴史を見れば、広い地球上で、人類が持続的に文明を築き、存続させた地域の植生域は極めて限られる。その代表は、日本・中国などの照葉樹林域、南欧の硬葉樹林域、北大西洋両岸の夏緑広葉樹林域である。
地中海沿岸では、紀元5世紀頃までに原植生の硬葉樹林(常緑のカシなど)を伐採し尽くした。中欧を被っていた夏緑広葉樹の原生林(ヨーロッパブナ、ヨーロッパミズナラなど)は、近世までに破壊された。主原因は火入れと放牧である。近年では、窒素質化学肥料の普及により、好窒素性牧草のみが旺盛に繁殖し、他の牧草を駆逐して本来の共存関係を乱している。欧州は環境問題に熱心だが、それは近代文明の破綻が、同地で真っ先に現れ始めたためである。
北米の自然破壊は18世紀中頃から本格化した。しかし欧州の惨状に学び、その轍を踏まなかった。例えばエマーソン(R.W.Emerson 1803-1882)のような、人間と自然の共存を唱える先駆者が現れた。1872年には世界初の国立公園(イエローストーン)を指定した。
日本民族を育てたのは照葉樹林(クス、カシ類など。常緑広葉樹林とも)である。とりわけ西日本ではそう言える。照葉樹林帯は中国を中心にアジアの南東部から日本に及ぶ。中国は四千年の文明の代償として、森林を破壊し尽くした。日本でも森林破壊は進んだが、宗教的タブー意識に支えられ、社寺林に原初の姿が残る。鎮守の森である。
森林は必ず緩衝植生帯に囲まれており、岩場、川、湖沼、裸地などと直接に接することはない。緩衝植生帯はツル植物や低木などの「マント群落」と、その外側に育つ多年生草本植物などの「ソデ群落」とに大別できる。
マント群落、ソデ群落などの緩衝植生帯が開発工事等で破壊されると、急に林内に光や風が入り、林床が乾燥するなどして森林全体が傷む。一方で森林とマント群落、ソデ群落の間にも緊張関係がある。東南アジアのジャングルには、高木が伐られて空間に空きが生じ、そこにツル植物が増殖繁茂して形成したものがある。
以上を踏まえれば、植物群落には独自の生理があり、常に最終相に向けてゆっくりと動いていることがわかる。ところがこの数千年、人類という「ノイズ」が、そうした自然の動きをあれこれ操作してきたのだ。=続く(プラチナ構想ネットワーク理事 長澤光太郎)