How to create the future beyond legal barriers: Purpose and courage change society
Updated by 小宮山 宏 on September 11, 2025, 9:26 AM JST
Hiroshi KOMIYAMA
(一社)プラチナ構想ネットワーク
東京大学工学部教授、工学系研究科長・工学部長、東京大学総長(第28代)を経て、2009年三菱総合研究所理事長に就任。2010年プラチナ構想ネットワーク会長(2022年 一般社団法人化)。その他、STSフォーラム理事長、一般社団法人超教育協会会長、公益財団法人国連大学協力会理事長、公益財団法人国際科学技術財団会長、一般財団法人 ヒートポンプ・蓄熱センター理事長など。また、ドバイ知識賞(2017年)、イタリア連帯の星勲章(2007年。)や「情報通信月間」総務大臣表彰(2014年)、財界賞特別賞(2016年)、海洋立国推進功労者表彰(2016年)など、国内外の受賞も多数。
私たちは日々、様々な法律や規制の中で生活しています。一見すると、これらのルールは私たちの行動を制限し、新しい挑戦を阻む「壁」のように感じられるかもしれません。しかし、私はそうは思いません。法律や規制は本来、社会を守り、人々が安心して暮らすための「道具」であるべきです。そして法律には必ず「趣旨」があるはずです。もし私たちが、法律の文言に縛られるのではなく、その根本にある「趣旨=目的」を深く理解し、それに沿って勇気をもって行動するならば、未来を拓く道は必ず見つかります。法律を単なる障壁と捉えるのではなく、未来を創るための強力な仕組みとして活用できるのです。
法律の壁の例として、私の著作『バイオマス・ニッポン』で紹介したバイオマス地域冷暖房の導入事例を考えてみましょう。森林で発生する端材などのバイオマス燃料を使って、地域に冷暖房を供給するシステムは、持続可能な社会に向けて非常に有効です。しかし、これを実現しようとすると、道路占有許可など、村道、町道、国道といった様々なレベルで複数の許認可が必要となり、70以上もの法律・規制の壁があることがわかりました。
では、なぜ多くの人にとって法律が「壁」に見えてしまうのでしょうか。これには日本の法体系と、私たち自身の思考様式が関係していると私は考えています。
日本の法体系は大陸法系と言われています。これは「やっていいこと」が明示されていない限り、原則として「やってはいけない」という考え方です。これに対し英米法では、「やってはいけないこと」が明示されている以外は原則自由です。この違いが、新しい挑戦を阻む大きな要因になっていると感じています。法律に書かれていない新しい試みは、許可を得るのが非常に難しくなるのです。
加えて、現代の日本社会には「大局観の欠如」が蔓延しているようにも見えます。個別の問題には熱心に取り組むものの、全体像を描いて語れる人が少ない。学術界でも、論文を書くために「部分最適化」に走りがちで、総合的な視点が失われているという議論があります。このような状況では、法律も個々の条文にばかり注目され、その背景にある大きな目的が見失われがちになるのです。
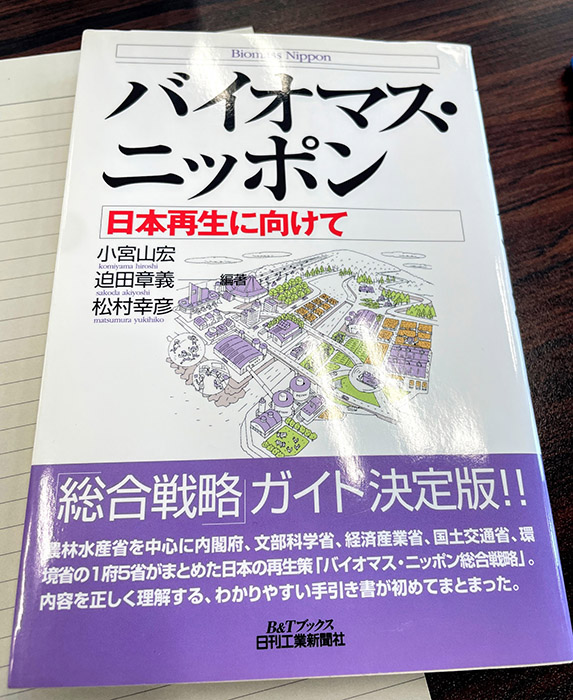
しかし、法律の「趣旨」を深く理解すれば、一見乗り越えられない壁も突破できる例は少なくありません。
例えば、木造建築の規制緩和です。かつて木造建築は、鉄筋コンクリート建築に比べて耐用年数や耐震性の面で融資に不利な扱いを受けていました。法律上も、高い木造建物を建てるのが難しかったのです。しかし、建築技術の進歩によって、木造でも鉄筋コンクリートと同等の耐震性や耐火性を確保できるようになりました。この技術的進歩が、法律の「耐震・防火の安全性」という目的を満たしたことで、規制は緩和され、現在では木造高層建築も増えつつあります。
法律の条文の背後には、社会が達成しようとする「趣旨=目的」が必ず存在します。この目的を深く理解し、その達成に貢献する行動であれば、たとえ法律の文言と異なるように見えても、道は開けるのです。
法律の趣旨を理解するだけでなく、それを現実のものにするためには、「勇気ある行動」が不可欠です。
特定集団の人々の採血から健康状態を知るというスタートアップの例をあげてみます。採血にあたって「医療従事者でないものが採血すると傷害罪にあたる」可能性がありましたが、「社会全体の健康状態を把握する」という大きな目的にため、そのスタートアップは、法律で定められている「人の血を取る」行為でなく「自己採血」であれば、法律に抵触しないと考え、法律の壁をクリアしたと聞いています。
役所側は、前例のない新しいことに対しては「積み置き」にしてしまうことが多いように感じます。誰も責任を取りたがらないため、新しい試みはなかなか前に進みません。しかし、私は「結局、やっちゃうやつがいる以外ない」と思っています。法律の趣旨を外さず、勇気をもって行動し、最初に実績を作った事業者が現れることで、初めて制度改善のきっかけが生まれるのです。
法律の壁を乗り越え、未来を創るためには、多様な利害関係者の間で「新しい合意形成の方法」を模索することも重要です。
規制緩和や制度改正には、多くの人々の理解と協力が不可欠です。しかし、それぞれが自分の立場から主張を繰り広げると、合意に至るのは困難です。ここで、私は生成AIの活用に大きな可能性を感じています。生成AIは、膨大な情報を分析し、対立するアジェンダや意見を整理するのに役立つかもしれません。
もちろん、AIに「正しいこと」を聞くだけでは不十分です。公文書や専門家の知見といった「優れた文章」をAIに学習させ、我々が「おかしい」と感じる点について議論を重ねることで、より精度の高い、建設的な合意形成を支援するツールになり得ると考えています。重要なのは、AIを単なる意見集約ツールとして使うのではなく、「法律の趣旨=目的」という共通の視点を持って議論を進めることです。この目的を見据えた上で、AIの力を借りて利害調整を行い、社会全体として納得できる解を見つけ出すことが、未来を拓く鍵となるでしょう。
日本の社会には、「みんなが黙ってしまう」という問題があります。しかし、社会を動かすのは、個々人の行動と発言の積み重ねです。たとえ小さな一歩であっても、法律の趣旨に則り、未来を見据えて「やっちゃう」勇気を持つ人が増えれば、制度は変わり、社会は変わっていきます。
私たちが、循環経済をはじめとする持続可能な社会の実現に向けて、積極的に発言し行動していくこと。それこそが、法律を真に未来に生かす力となるでしょう。(プラチナ構想ネットワーク会長 小宮山宏)
【新刊】『森林循環経済』好評発売中!
当Webメディアと同名の書籍『森林循環経済』(小宮山宏 編著)が平凡社から8月5日に刊行されました。森林を「伐って、使って、植えて、育てる」循環の中で、バイオマス化学、木造都市、林業の革新という三つの柱から、経済・制度・地域社会の再設計を提言しています。政策立案や社会実装、地域資源を活かした事業づくりに携わる方にとって、構想と実例の接点を提供する実践的な一冊です。
Amazonで見る