France, which has achieved forestry that imitates nature, is increasing production of large-diameter hardwood timber
Updated by 長澤 光太郎 on September 24, 2025, 9:05 PM JST
Kotaro NAGASAWA
(一社)プラチナ構想ネットワーク
1958年東京生まれ。(株)三菱総合研究所でインフラストラクチャー、社会保障等の調査研究に従事。入社から数年間、治山治水のプロジェクトに携わり、当時の多くの河川系有識者から国土を100年、1000年単位で考える姿勢を仕込まれる。現在は三菱総合研究所顧問。学校法人十文字学園監事、東京都市大学非常勤講師を兼ねる。共著書等に「インフラストラクチャー概論」「共領域からの新・戦略」「還暦後の40年」。博士(工学)。
前回紹介した村尾行一著『森林業−ドイツの森と日本の林業』には、17世紀初頭のドイツは乱伐が原因で木材窮乏(独:Holznot)に陥り、回復に向けて「保続」の概念を編み出し、林業専門学校を設立したと書かれている。そして「教員は当初はフランス人カメラリスト(※)が主に就任した。当時のヨーロッパではなにかにつけフランスが先進国だったからである。そのフランス人教員が一番頭を抱えたのは、学問的素養がなく、ただただ経験を通してしか学んでいないドイツ人林業従事者のレベルの低さである」と続くのである。(※カメラリスト:行政研究者。「官房学者」とも)
素直に読めば、少なくともある時期、ドイツ林業の先を行く国としてフランスがあったことになる。残念ながら村尾氏は、フランス林業にそれ以上は触れていない。
フランス林業を解説する資料はあまり見つからないのだが、昨春すばらしい書籍が発刊されていた。それが門脇仁氏の『広葉樹の国フランス』である。今回はKindleで読むことにした。
単行本で300頁に及ぶ中身の濃い本である。全体は三部構成で、フランスの森林と林業の紹介、その歴史、そして日本との比較である。私はドイツの歴史からフランスに関心を持ったので、原著の構成とは異なるが、まず前編は歴史について、後編はフランスの森林と林業の特徴そして日本との比較について、それぞれ面白かった部分を紹介したい。
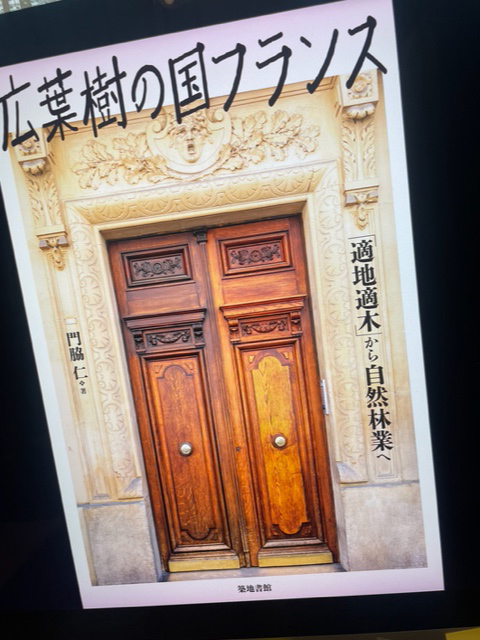
フランスはもともと森林に恵まれており、ローマから遠征してきたカエサルも、その後大移動してきたゲルマン民族も、豊かな森林資源を燃料あるいは建材、造船などに大いに利用した。この地に住む人々は萌芽更新(伐採した樹木の切り株や根元から生える新芽を選択的に育成する更新方法)の技術を獲得していたため、古代における森林破壊は一定の範囲内で防がれた。
大規模な森林破壊は中世から始まる。8世紀頃から当時のフランク王国が開墾を奨励し、やがて急増した修道院が活動(修道僧の「お務め」か)の一環として精力的に開墾を行なったり、人口増もあって13世紀頃まで約500年の乱伐期間が続いた。
十字軍の失敗で法皇庁の権威が低下し、王権が伸長する中で王室財産としての国土をどう管理するかという問題意識が生まれてきた。1291年にフィリップ四世は「水・森林管理官」という役職を設置し、1346年にフィリップ六世がそれを組織化して「王室治水森林局」を設置した。確かに、同時代の日本(鎌倉時代)やドイツ(神聖ローマ帝国の一部)と比べて非常に先進的である。
フランスの木材需要が急増したのは15世紀からである。工業が発展して燃料や素材の需要が増加し、盗伐や乱伐が広がった。
王室もこの問題を無視できなくなり、ルイ十四世(1638年〜1715年)は、腹心の財務総監ジャン・バチスタ・コルベール(1619年〜1683年)に対策を問う。コルベールはブルボン朝の財政再建で知られるが、土木出身の私にとってはミディ運河に予算をつけた人である。このフランス横断運河は、大西洋から地中海まで、ジブラルタル海峡を経由しない超短距離船舶輸送を可能にした。また彼はイタリアから天文学者カッシーニを招聘し、正確な測量でフランス全図を作る大プロジェクトの糸口を作った。つまり単なる財政再建のプロではなくて、時代を創る基盤整備にしっかり投資した人である。
コルベールは考えた。すでに14世紀から王室治水森林局はある。これを活かさない手はない。そして時代のニーズは建艦(針葉樹:官需)と燃料・建材(広葉樹:民需)だ。それらを考え合わせれば複層林(針葉樹と広葉樹をミックスした森林)で行くのが良い。
コルベールは1669年にいわゆる「森林大勅令」を発出。適用範囲は林地のみならず水源、木材水運、狩猟、漁労など森林に関わる全ての領域に及ぶ。あらゆる階層が所有する森林に定期的な伐採を含む施業を義務付け、森林保全の細かな規則を制定。林務官が私有林に行使できる権限を拡大し、王室林がもたらす利益は全て国庫収入とした。フランスの森林経営は根底から整備し直された。この改革により王室林収入は6倍増、造船用木材も確保され、工業発展の基盤が整えられた。17世紀初頭にドイツで指導にあたったフランス人は、おそらくこの王室林収入増を支えた人々だろう。
コルベールが築いたフランスの森林経営体制は、100年後のフランス革命で転換期を迎える。王政を打倒した革命政府は王室や僧院や亡命貴族の所有林を解体して国有林とし、その一部は国民に譲渡された。私有林や市町村有林への国の関与は禁止され、林務官は全員更迭された。この影響は現代にも及んでおり、フランスの国有林は森林全体の9%に過ぎず、私有林は75%で、1ha未満の零細な個人経営が多い。森林管理が緩やかになり、産業需要が拡大したことで、19世紀初頭フランス森林の国土面積比率は史上最低の13.6%まで落ち込んだとされる。
ただし、複層林を重視する森林づくりはフランス革命後も概ね維持されて今に至っている。ドイツの成功に刺激されて、フランスでも大規模一斉単純林方式への関心が高まった時期もあるが、結果としてそれは主流にはならなかった。
1980年代には拡大する林産物需要に対して複層林の低生産性が課題となったが、議論の末に採用されたのは広葉樹大径材の増産であった。著者の門脇氏はこれを広葉樹へのこだわりを貫くフランスらしさと評している。
広葉樹大径材の増産は国策として進められ、補助金や投資信託が利用できたので零細な私有林の林業経営にも徐々に浸透。30年後(2010年代)には広葉樹の高林が育ち、2023年末の森林率は32%まで回復したとされる。19世紀初頭に比較して2.4倍である。
著者は言う。「人間社会のニーズによって改変された自然ではなく、それぞれの土地の潜在自然植生や風土に立ち返り、できる限り本来の生態系に近い森を取り戻すことが、世界的にも林業の課題といえる」「適地適木を徹底し、地方分権改革も導入しながら『自然を模倣する林業』を実現してきたフランスは、その営みに先鞭をつけたといっていい」
隣国ドイツの、針葉樹の大規模一斉単純林方式による林業生産性向上を横目で見ながら、フランスはついに同じ方向を向かなかった。その根底には適地適木の考え方と、フランス人はもともと広葉樹に特別の想いを持っていたことがあるという。この点については後編に記す。(プラチナ構想ネットワーク理事 長澤光太郎)
■関連サイト
広葉樹の国フランス (築地書館)