The "mother of Japanese street trees" - the tulip tree - spread from Shinjuku Gyoen to the rest of Japan
Updated by 渡辺一夫 on November 14, 2025, 6:48 PM JST
Kazuo WATANABE
森林インストラクターとして、樹木の知識の普及や、自然環境を解説する活動を行っている。NHK文化センター、毎日文化センター、よみうりカルチャー、NHK学園などで講師をつとめる。著書は、『公園・神社の樹木』『街路樹を楽しむ15の謎』『アジサイはなぜ葉にアルミ毒を溜めるのか』(以上築地書館)など。1963年横浜生まれ。東京農工大学大学院修了。農学博士。
広々とした公園で、大きな木を眺める。そんな気分のよい散策ができる公園に新宿御苑がある。新宿御苑は、東京都新宿区、都心のど真ん中にある公園である。面積約60ヘクタールの広大な園内には、西洋式庭園と日本庭園が広がり、さまざまな樹木がある。都心とは思えないような静かな園内には、プラタナス、ユリノキ、ヒマラヤシーダーなどの大きな樹木が見られる。これらの大きな木が植えられたのは、明治時代にさかのぼる。
新宿御苑がある場所は、江戸時代には高遠藩主であった内藤氏の江戸屋敷であった。その後、明治時代になると国のいわゆる「農業試験場」となり、野菜や果樹の栽培、養蚕、牧畜などの研究が行われるようになった。樹木の研究も行われ、試験場内にさまざまな種類の樹木、特に、ユリノキ、プラタナス、ヒマラヤシーダー、ラクウショウ、アメリカキササゲ、タイサンボクなどの外来の樹木が植えられた。その後、皇室庭園の時代を経て、1949年に公園として開放され、現在ではそれらの樹木は大木に育っている。
新宿御苑は広大な面積をもつ公園であるが、その中心にはひろびろとした芝生の広場がある。「風景式庭園」と呼ばれるこの芝生広場に、高さは30mを超えるという大きなユリノキがそびえている(写真1)。近くで見ると、3本のユリノキが身を寄せ合って、まるで一本の巨大な木であるかのように生い茂っている。新宿御苑には約30本のユリノキがあるが、中でも風景式庭園にあるものは、ひときわ際立って大きく、新宿御苑のシンボルツリーになっている。ユリノキの原産地は北米であり、北米では高さ50mを超えることがあるという。新宿御苑のユリノキは、明治時代に持ち込まれ植えられた。

ユリノキは大きな花をつける木である。花は、百合というよりも、チューリップのような形をしている。黄緑色の花弁にはオレンジ色の紋が入っていて美しい(写真2)。また、この花は蜜を多く出す。かつて新宿でも養蜂が行われていた時代には、新宿御苑のユリノキが蜜源になっていた。背丈が大きくなる木であり、花は高い位置に咲く。したがって、その姿を見る機会はなかなか無いが、もしユリノキが街路樹として植えられていたら、ビルの窓や、歩道橋の上から楽しむことができる。花の時期は初夏である。葉の形もおもしろい。Tシャツの形をしている。ユリノキは別名ハンテンボク(半纏木)とも呼ばれる。それは葉の形が半纏に似ていることが語源だ(写真3)。


ユリノキは樹形が美しい上に、寒さや病害虫にも強い。このため街路樹や公園樹として植えられている。ユリノキが日本に持ち込まれた明治時代に、この木を評価し街路樹として普及させた人物に、福羽逸人(ふくばはやと、1856年~1921年)がいる。福羽は、宮内省の園芸技術者であり、ブドウ、メロン、イチゴなどの品種改良において多大な功績を遺している。また街路樹・公園樹の研究における貢献も大きい。そして、新宿御苑の総指揮者でもあった。
都市の近代化という時代の要請に答えるため、福羽はどのような樹木が街路樹や公園樹に適しているかを調べ、ユリノキ、プラタナス、ヒマラヤシーダーなどの樹木の普及に尽力した。さらに福羽は、新宿御苑のユリノキやプラタナスの種子や挿穂を、大量に東京市に寄付し、東京の街路樹の苗木を育成する契機となった。
このような機縁を得て、東京に街路樹を普及させたのが、東京市の職員であった長岡安平(1842年~1925年)である。長岡は公園の建設や街路樹の普及をとおして、東京市の緑化を推し進めた人物である。彼は、乏しい予算の中で、東京市内に街路樹の苗木を育てる土地(苗圃)を探し、自らクワをふるい、数万本もの街路樹の苗木を育てていった。特にユリノキをこよなく愛し、ユリノキの街路樹を広めていったのである。
新宿御苑のユリノキは、明治期に日本に持ち込まれたものである。このユリノキを母樹として、その種子を用いて各地にユリノキが植えられた。例えば、赤坂の迎賓館前には、美しいユリノキの並木がある。この並木は明治時代の末に赤坂離宮(旧東宮御所)が完成した際に、新宿御苑のユリノキの種子から育った苗木を植えたものだ。さまざまな場所に植えられた新宿御苑のユリノキの二世も、今ではすでに大きく育っている。
新宿御苑には、ユリノキのほか、プラタナスやヒマラヤシーダーといった大きな木がある。これらも明治期に外国から収集し、植えられたものだ。これらの木は、造園や緑化の技術者によって研究され、街路樹として、あるいは公園樹として全国に広まり、活躍してきた。
ユリノキは堂々と大きくなる木である。そして、かわいい花も咲かせる。蜜の甘い香りも放つ。その魅力に魅せられた人々の手によって、新宿御苑の地から、東京、さらには全国に広まっていった。そして、公園や街路樹の整備を通じて、都市の近代化を成し遂げる一助となった。新宿御苑の母なるユリノキは、その歴史を今も見守り続けている。(森林インストラクター 渡辺一夫)
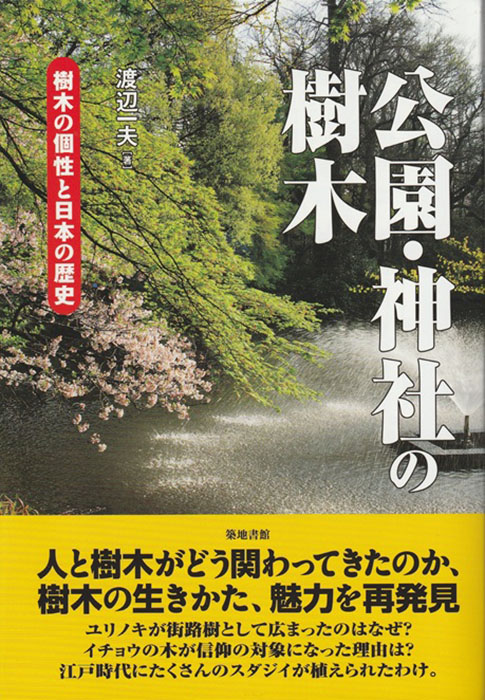
『公園・神社の樹木』
渡辺一夫著、築地書館刊
人々に愛されている緑のオアシス、そこに秘められた歴史やエピソードを紹介する。公園・神社の樹木を通して、人と樹木がどう関わってきたのか、樹木の生きかた、魅力を再発見する本。
<目次>
第1章 眠れなくなったプラタナス
第2章 戦争に翻弄されたツツジとハナミズキ
第3章 水郷の歴史を語るエノキ
第4章 江戸の大火と戦ったスダジイ
第5章 台湾からやってきたクスノキ
第6章 渋沢栄一は、なぜ公園を造ったのか?
第7章 イチョウが拝まれるようになったわけ
第8章 サクラの丘に秘められた5000年の歴史