Time to rethink the “hidden wealth” of forests
Updated by 小宮山 宏 on May 13, 2025, 3:58 PM JST
Hiroshi KOMIYAMA
(一社)プラチナ構想ネットワーク
東京大学工学部教授、工学系研究科長・工学部長、東京大学総長(第28代)を経て、2009年三菱総合研究所理事長に就任。2010年プラチナ構想ネットワーク会長(2022年 一般社団法人化)。その他、STSフォーラム理事長、一般社団法人超教育協会会長、公益財団法人国連大学協力会理事長、公益財団法人国際科学技術財団会長、一般財団法人 ヒートポンプ・蓄熱センター理事長など。また、ドバイ知識賞(2017年)、イタリア連帯の星勲章(2007年。)や「情報通信月間」総務大臣表彰(2014年)、財界賞特別賞(2016年)、海洋立国推進功労者表彰(2016年)など、国内外の受賞も多数。
「日本は資源のない国だ」。こうした言葉を、私たちは学校やニュースで何度も耳にしてきました。だからこそ、エネルギー安全保障が大切なのだと。だからこそ、資源輸入に頼らざるを得ないのだと――。けれど、果たして本当にそうでしょうか。日本は本当に、資源に乏しい国なのでしょうか。今あらためて、その問いを見つめ直す必要があります。
実は、日本の国土の約3分の2は森林に覆われています。先進国の中でも非常に高い森林率であり、世界に誇れる緑の密度を持つ国です。そしてこの森林は、木材という“再生可能な資源”の宝庫でもあります。つまり、「ない」と思われてきた資源が、実は“目の前にある”のです。
では、なぜ「日本は資源がない」と言われ続けてきたのでしょうか。それは、これまでの日本社会が、地下資源――石油、石炭、鉄鉱石といったもの――を「資源の基準」としてきたからです。地下から掘り出し、精錬し、燃やし、加工して使う。こうした“一度使ったら終わり”の使い切り型の資源利用が、20世紀の日本の成長を支えてきました。
その時代には、森林の価値は十分に評価されていませんでした。木は使い勝手が悪く、育てるのに時間がかかり、効率が悪いと見なされてきたのです。加えて、安価な輸入材の増加が拍車をかけ、国内の林業は次第に衰退していきました。結果として、国産材の自給率は大きく下がり、森林が持つ本来のポテンシャルが活かされないまま、長い時間が過ぎてきました。
その一方で、日本の人工林の多くは、すでに伐採に適した年齢を迎えています。たとえばスギやヒノキなど、戦後の復興期に一斉に植えられた木々は、50年、60年と経ち、資源として最も価値のある時期に入っています。それにもかかわらず、十分に伐られず、使われず、手入れもされないまま放置されている山が全国に広がっています。つまり日本には、実際には豊かな森林資源が存在しているのに、それを活かすしくみが滞っているという状況があるのです。
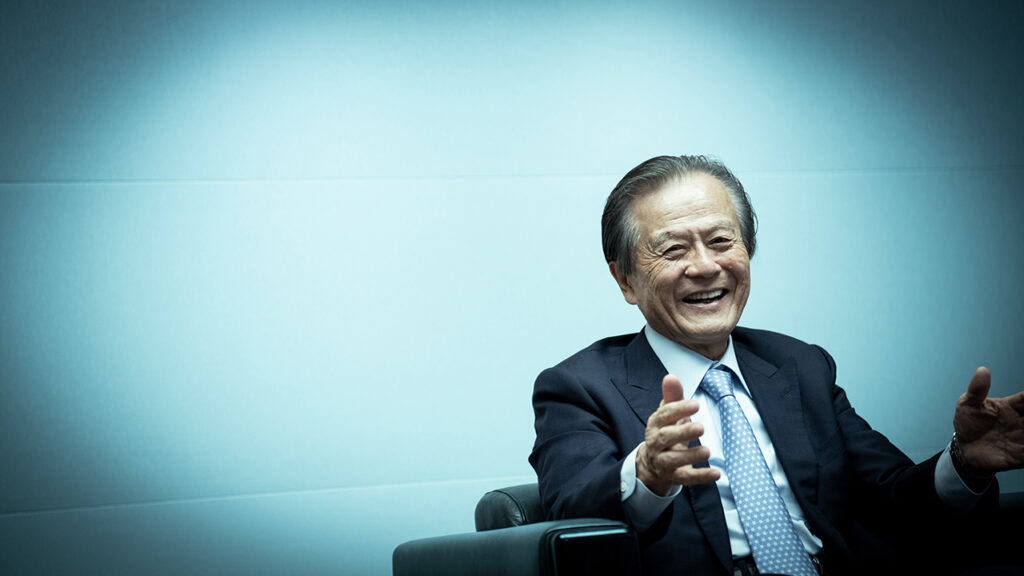
ここで視点を変えてみましょう。地下資源は、一度掘って使えば終わりです。しかし、森林は違います。木を伐っても、そこにまた苗を植え、育てることで、次の木が成長します。時間と手間はかかるけれど、同じ場所から何度も資源が生まれるのです。つまり森林は、「再生可能な資源のモデルケース」と言える存在です。しかもその資源は、国内で完結できるものです。輸入に頼る必要がなく、エネルギー安全保障や経済の安定にもつながります。木材だけではありません。森林をめぐる産業には、バイオマス燃料、バイオプラスチック、医薬品原料、水源保全、観光など、さまざまな可能性が広がっています。
さらに重要なのは、森林が炭素を蓄える「自然の貯蔵庫」であるという点です。気候変動への対応というグローバルな課題において、木を伐って育てるという“森林の循環利用”は、CO2を大気から引きはがし、長く固定するためのひとつの有効な手段となり得ます。私たちは今こそ、「資源=地下にあるもの」という時代の価値観から抜け出す必要があります。そして、日本が本来持っている“地上の資源”、すなわち森林という再生可能資源を、もう一度見直すべき時期にきています。資源がない国なのではなく、使われていない資源がある国。使い方を間違えてきた国。でも、これからはその資源を「守りながら、育てながら、使う」方向へと社会のしくみを変えていくことができます。
木を、森林を、そして森を支える産業全体をもう一度動かす。それこそが、私たちが次の世代に向けて選ぶべき「持続可能な成長のかたち」なのです。(プラチナ構想ネットワーク会長 小宮山宏)
当Webメディアと同名の書籍『森林循環経済』(小宮山宏 編著)が平凡社から2025年8月5日に刊行されました。森林を「伐って、使って、植えて、育てる」循環の中で、バイオマス化学、木造都市、林業の革新という三つの柱から、経済・制度・地域社会の再設計を提言しています。政策立案や社会実装、地域資源を活かした事業づくりに携わる方にとって、構想と実例の接点を提供する実践的な一冊です。
Amazonで見る